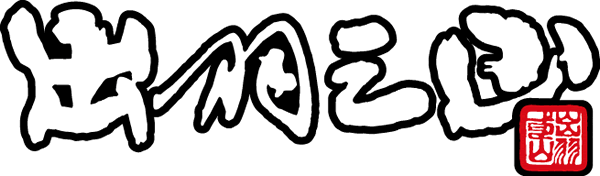
| 出羽三山の「羽黒山」「月山」「湯殿山」は深い信仰の対象で、推古天皇の時代に開山され次第に羽黒派の修験道が発達し、ほら貝で有名な羽黒の山伏達が三山を修業の場として全国に広め、古くから山岳信仰の聖地として栄えてきました。 現在でも多くの発拝者を迎え、夏から秋にかけては白装束の人々が山頂を目指して行きます。信者の多くは羽黒山に始まり、月山に登って、湯殿山に下り、三山の神社をお参りします。 |
  |
  |
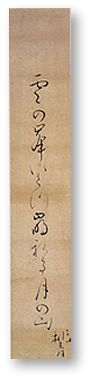  |
| 元禄2(1689)年6月3日〜9日、松尾芭蕉が「奥の細道」行脚の途次に出羽三山に逗留しました。羽黒権現に詣で、月山に登った芭蕉は、山頂で一泊した後、湯殿山に下り、坊に帰って阿闍梨の求めによって、三山巡礼の句々を、短冊に書いています。 涼しさやほの三日月の羽黒山 雲の峰いくつ崩れて月の山 語られぬ湯殿にぬらす袂かな そして、羽黒を後にした芭蕉でした。 「奥の細道」、そして芭蕉が書き残したこれらの名句の数々は、多くの文人墨客を惹きつけ、今もなお、たくさんの人々が、芭蕉の足跡を訪ねて出羽三山に来山しています。 |
| 男山酒造 出羽三山(1800ml、720ml) | |||
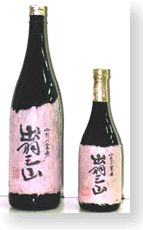 |
由来
特長 |
||
| 出羽三山 | ヤマモトTOPへ |
この商品に対するお問い合わせは こちら
までお気軽にどうぞ。
